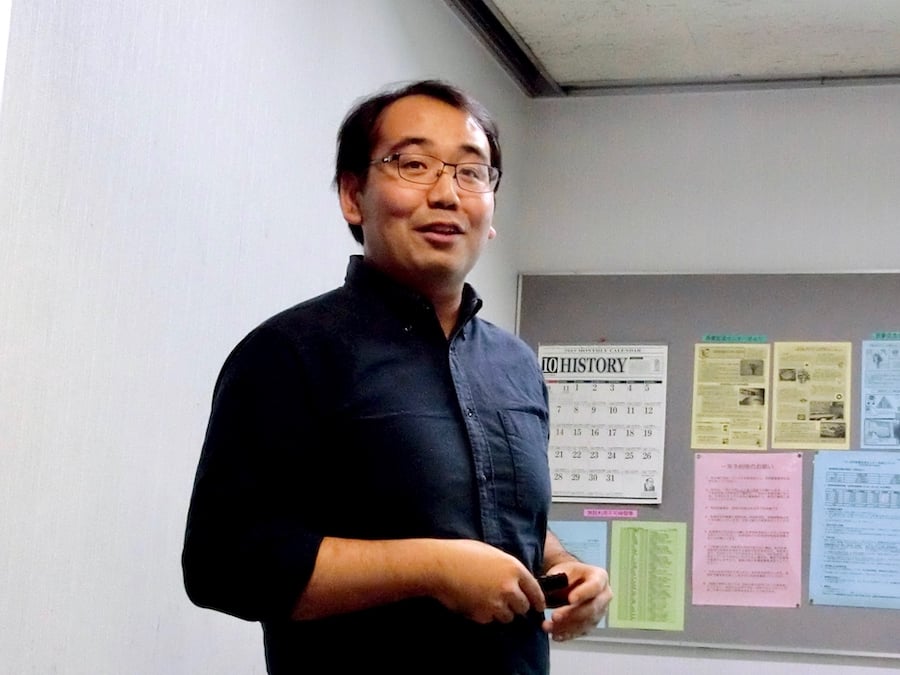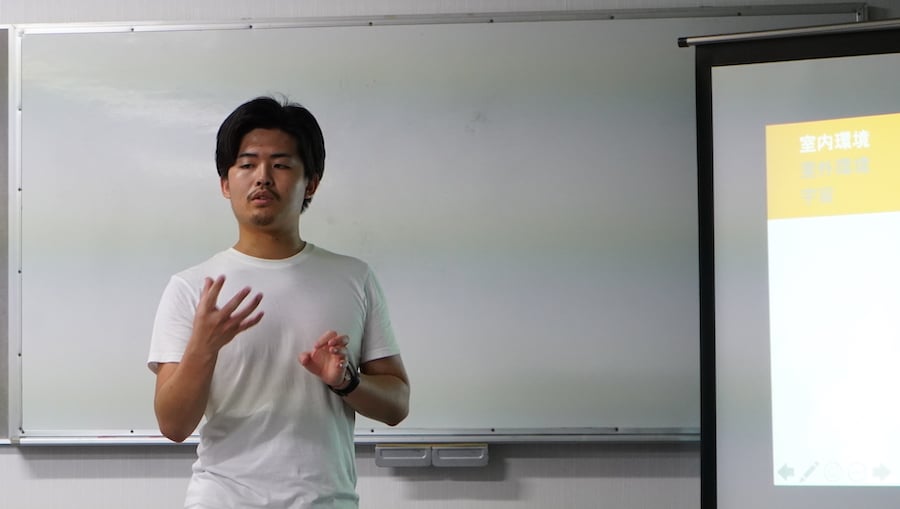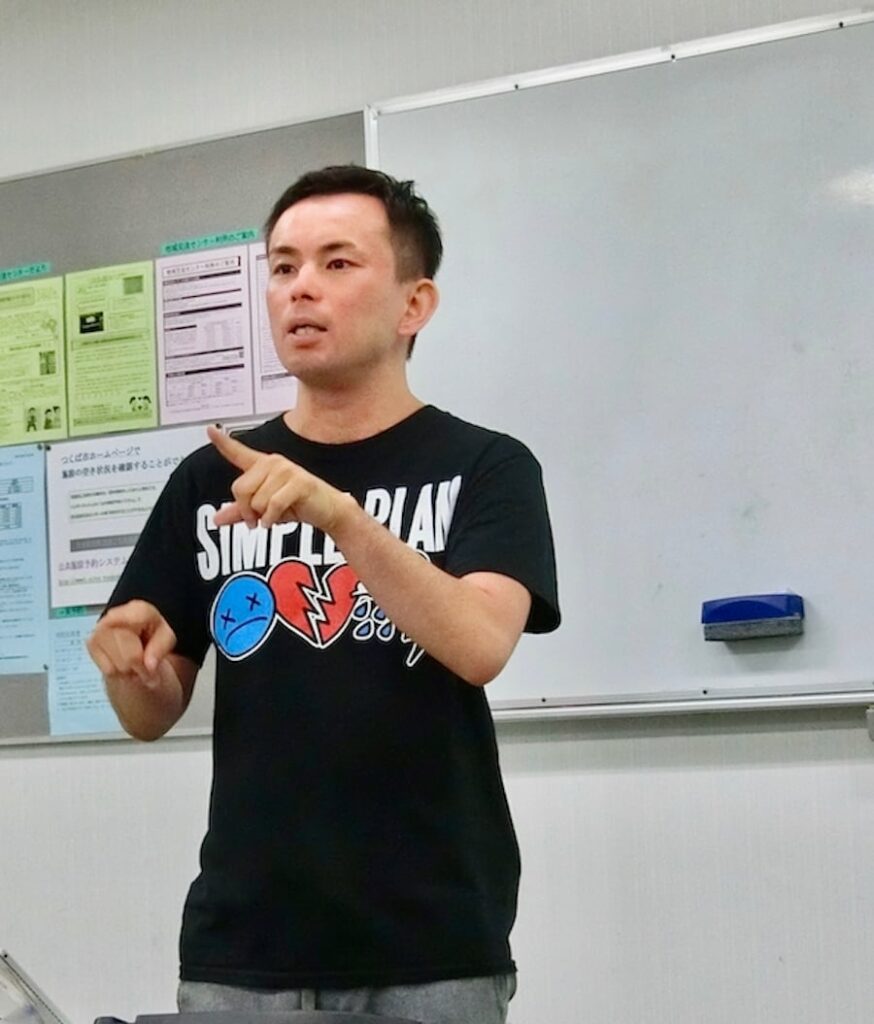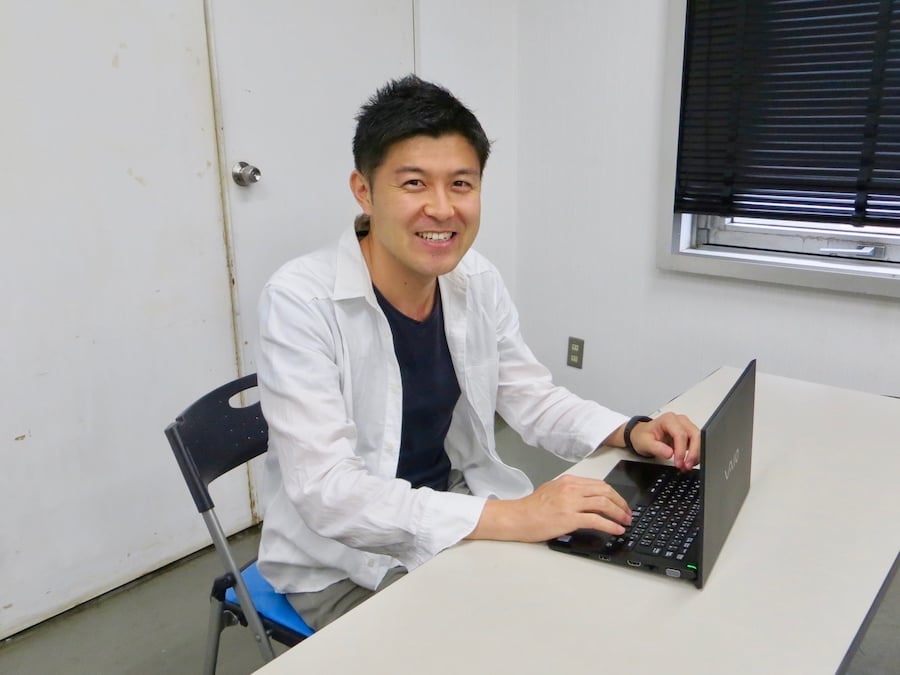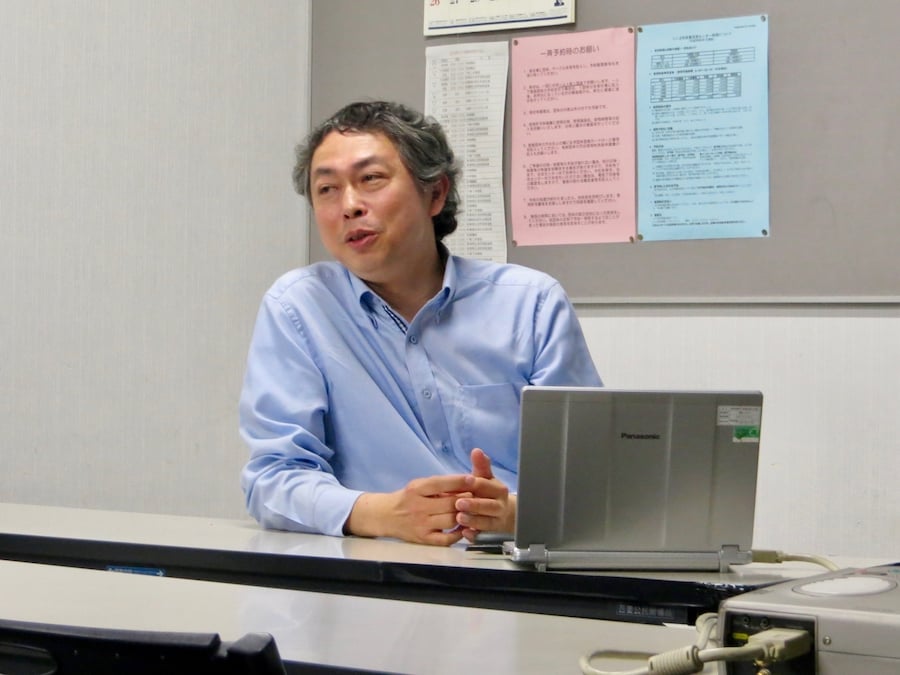2021年10月23日(土)16:00 ~ 18:30
場所:オンライン
第33回の交流会では、前半は齋藤 隆一さん(東亜薬品工業株式会社)に、後半は鹿野 豊さん(群馬大学 / チャップマン大学量子科学研究所 / JSTさきがけ)にそれぞれご講演いただきました。
———
発表者:齋藤 隆一さん(東亜薬品工業株式会社)
タイトル: 腸内細菌叢とプロバイオティクス
腸内細菌叢は第二の臓器とも言われ、我々の健康に大きく関与しています。腸内細菌叢の乱れは、感染症や腸炎だけでなく、癌、糖尿病や自閉症などの様々な疾患の発症に関与していることが示唆されております。
そして、プロバイオティクスとして用いられている細菌は、この腸内細菌叢の乱れを回復することで、様々な疾患の治療·改善することが知られており、現在非常に注目されています。
今回は、腸内細菌叢の働きと、プロバイオティクスの効果や課題について我々の臨床研究結果を交えてご紹介させて頂きます。
———
発表者:鹿野 豊さん(群馬大学 / チャップマン大学量子科学研究所 / JSTさきがけ)
タイトル: 世界は本当にデタラメなのか?~理論物理学者からの考察~
「神はサイコロを振らない」というのは、2015年に結成された4人組のロックバンド名でもあるが、20世紀を代表する理論物理学者 Albert Einstein の有名な一言である。この背後には、Albert Einstein の量子力学という20世紀初頭に誕生した新しい世界観を受け入れらないというものであった。一方、世界がランダムであるかどうかの論争は紀元前の「骨転がし」の時から始まり、現在まで、もしかしたら複雑な決定論的な法則によって支配されている可能性を否定できない。そのため、デジタル計算機における最初の応用事例の一つは John von Neumann が考えた「疑似乱数生成機」であった。その後、応用数学·暗号理論の発展により、疑似乱数の理論は発展していくが、この世の中を記述する方法論として原理的に確率的な記述でなければならないか?ということは検証すべき研究課題である。そうすることで、本質的に確率的な記述が必要である量子力学の基盤を検証することが出来ると考えられている。そこで本発表では、乱数の歴史を哲学·物理学·統計学·確率論の歴史と交えて紹介し、乱数の尺度をどのように定量化するかについて情報科学的な観点を導入することで紹介し、自身の量子乱数生成の研究について紹介する。
———