2015年8月8日(土) 15:00 ~ 17:30
場所:吾妻交流センター
第10回の交流会では、前半は花田智さん(産業技術総合研究所)に、後半は保田敦司さん(筑波大学)に、それぞれご講演を行っていただきました。
前半の花田さんには、ご自身で新しく発見した微生物や、微生物が引き起こす”変敗”の実際に起きた様々な例や仕組みといった内容をご講演いただきました。身近に起きている様々な現象に微生物が関わっていることを知ることができた、大変おもしろいご講演でした。
後半の保田さんには、筑波大学の学生が中心となって開発している小さな人工衛星”Cubesat”に関するご講演をいただきました。一号機で得られた知見をもとにして現在二号機の開発中とのことで、将来人工衛星が打ち上がるのが楽しみになるご講演でした。
———
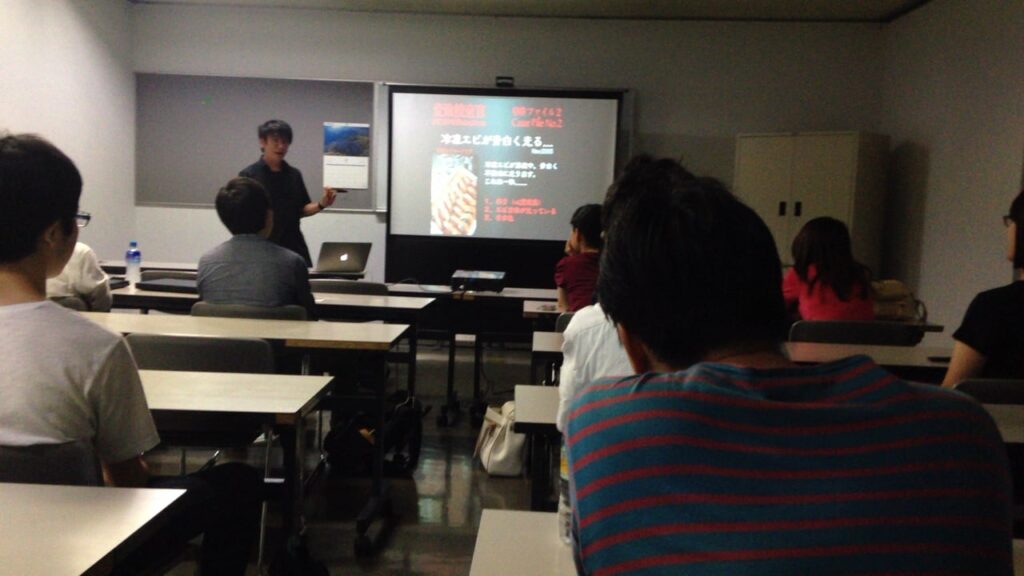
発表者:花田智さん(産業技術総合研究所)
タイトル:変敗捜査官の事件簿 ―食品変敗と原因微生物―
食品と微生物の良好な関係は様々な発酵食品に見られます。麹菌や酵母によって行われる味噌やお酒の醸造、乳酸菌によって作られるヨーグルト、チーズなど微生物が食品の風味を良くしたり、長期間保存するのに役立ってる例は枚挙に暇がありません。その一方で、微生物によって食品の風味が落ちたり、変色してしまったり、腐敗してしまうこともしばしば起きてしまいます。この様な食品の劣化は「食品変敗」と呼ばれていますが、それがどの様な微生物によって引き起こされたのかを科学的分析手法によって解明してきた課程を、「変敗捜査官の事件簿」と銘打ち、ミステリ仕立て(?)でお話ししたいと考えています。
———

発表者:保田敦司さん(筑波大学)
タイトル:超小型人工衛星「CubeSat」の新たな可能性~CubeSatと宇宙教育~
みなさんは「CubeSat」というものをご存知でしょうか.
CubeSatとは,1辺10cm,重さ数kgというごく小さな人工衛星のことを指します.
大型衛星に比べてコストの低さや開発期間の短さから,世界中の多くの大学や企業,研究機関が開発を行っています.
このCubeSatが世界で初めて打ち上がったのは2003年6月で,それから現在に至るまで,100機以上のCubeSatが世界中から打ち上げられました.
これらCubeSatは小さな衛星であるにも関わらず,数多くの科学的·技術的成果を挙げ,今やCubeSat開発は世界中でホットな研究の一つとなりつつあります.
今回はそのCubeSatの新たな使い方として,「CubeSatを宇宙教育に利用してみるのはどうだろうか.」という点に焦点を当てたお話をしたいと考えています.
最近は子どもたちの理科離れが騒がれている一方,2010年の小惑星探査機「はやぶさ」の帰還をきっかけに,子どもや大人を含めた幅広い年代から,宇宙や人工衛星への関心が集まっています.
そんな中,このCubeSatを宇宙教育に利用することで,理科教育や人材育成の効果が期待されると考えられます.
今回は「CubeSat」「宇宙教育」という2つのキーワードのもと,私が所属する筑波大学「結」プロジェクトのCubeSat「ITF-1」「ITF-2」を例に,CubeSatの宇宙教育への応用について紹介したいと思います.
———
