2015年6月27日(土) 15:00 ~ 17:30
場所:吾妻交流センター
第9回の交流会では、前半は佐藤那津未さん(Natsumi Satoh Global Communication Consulting)に、後半は岩瀬英治さん(早稲田大学)に、それぞれご講演をしていただきました。
佐藤さんには、「英語感覚」と「日本語感覚」の違い、それが元で生じてしまうコミュニケーションのギャップについて、分かりやすい例を交えてご紹介いただきました。言われてみれば覚えのある内容も多く、言語感覚という普段は意識しないものを意識していくきっかけになるご講演でした。
岩瀬さんには、「マイクロマシン」や「MEMS」といった、携帯電話など身の回りのものにも使われている「小さな機械」についてご講演いただきました。小さな世界では今の私たちの感覚がそのまま通用しなくなることや、そもそもこのような小さな機械をどのように作るのかといったことなど、いろいろな側面から「小さな機械」についてご紹介いただきました。
———

発表者:佐藤那津未さん(Natsumi Satoh Global Communication Consulting)
タイトル:あなたのプレゼンスをあげるグローバルコミュニケーション
英語でコミュニケーションをとる時、『英語感覚』と『日本語感覚』の違いどれくらい意識してますか?もしあなたの答えが『NO』もしくは『???』の場合は、あなたは論文や学会発表を通して、ポテンシャルを十分に発揮しきれていない可能性大です。
『英語感覚』と『日本語感覚』の相違が引き起こす、致命的なミスコミュニケーションやデッドコミュニケーション(全くコミュニケーションが成り立っていない状態)。そんな悲劇にあなたが巻き込まれないためにも、グローバルコミュニケーション力を培う上で日本人が陥りやすい『感覚のズレ』ポイントの傾向と対策について紹介していきます。
———
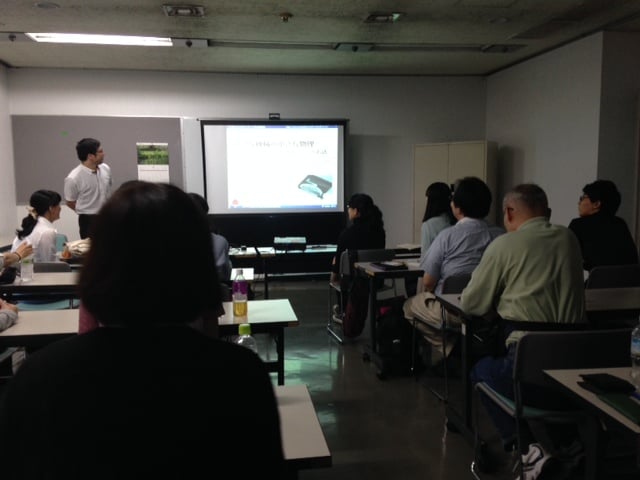
発表者:岩瀬英治さん(早稲田大学)
タイトル:小さな機械の小さな物理 ~マイクロマシンのお話~
「アリは壁を上れるのにゾウが出来ないのはどうして?」
「水は少量だと球状の“水玉”になるのに、多量だとそうならず“水溜り”になるのはなぜ?」
皆さんはこれらの疑問に答えられるでしょうか?
近年、小さいものを作る技術は非常に発達し、髪の毛の太さ程度の歯車や構造を作れるようになってきています。これは「マイクロマシン」「MEMS(Micro-electro-mechanical Systems)」と呼ばれ、スマートフォンや自動車にはこの技術を使ったセンサーなどが使われています。しかしながら、このような「小さな機械」を作るときに、大きな機械の設計図をそのまま小さくして作れば動くというわけではありません。これは、最初に挙げた身近な例からも想像できように、小さな機械·小さな世界に特有の物理現象がその前に立ちはだかってくるためです。小さな機械を作るには何を考えたら良いのか、小さな機械はどんな形をしているのか、大きさが変わるだけで世界がどう変わるのかなどについてお話したいと思っています。
———
