2019年10月26日(土) 16:00 ~ 18:30
場所:吾妻交流センター
第27回の交流会では、前半は新海陽一さん(産業技術総合研究所)に、後半は松本道生さん(物質·材料研究機構)にそれぞれご講演いただきました。
前半の新海さんのご講演では、線虫C. elegansのこれまでの様々な研究事例紹介や、親が獲得した形質の遺伝に関わる分かっていること/いないことなどをご紹介いただきました。これまでの遺伝に関する知識がまさに覆ろうとしている最先端の事例が分かる、とても面白いご講演でした。
後半の松本さんのご講演では、どのようにして原子を自在に配置した構造を作るのか、その構造の多様性をどのように担保するかといったことから、”分子ざる”として実際に水から不純物を取り除く事例まで、理論から実践まで幅広くご紹介いただきました。原子の組み合わせ次第で様々な応用のあり得る、非常に興味深いご講演でした。
———

発表者:新海陽一さん(産業技術総合研究所)
タイトル: 線虫研究からわかってきた新学説~親の努力を子供が受け継ぐ? ~遺伝子のその先にあるエピジェネティクス
カレーを食べたら猛烈にお腹が痛くなってそれ以来食べられなくなった、というような経験はありますか?もっと身近なところで例を挙げれば、最近になって花粉症になってしまった方はいらっしゃるでしょう。
こうした生まれた時には備えていない特徴や能力を獲得した場合、それらは子供に受け継がれるでしょうか?おそらく、この質問に対して、中学校の授業では、「No」と教えられただろうと思います。しかし、近年、それを覆す研究成果が、どんどんと報告されてきています。
今回、その研究成果の中心にある「エピジェネティクス」とは何か?私たちの病気とどのように関わっているのか?今話題の「相分離」とも関係するのか?などについて、私が扱う線虫C. elegansの研究を織り交ぜながら話題提供いたします。
———
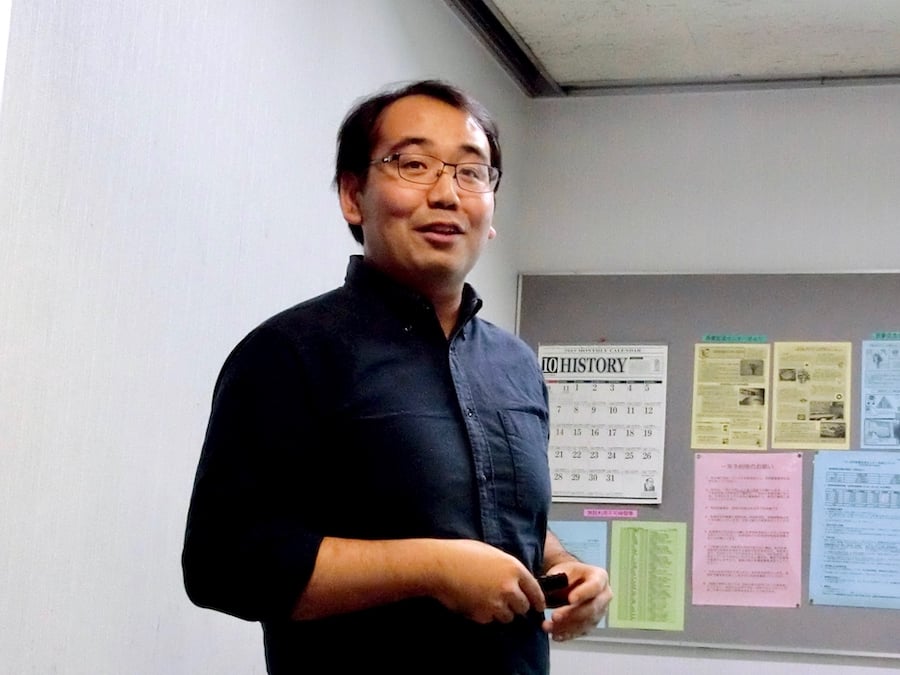
発表者:松本道生さん(物質·材料研究機構)
タイトル:原子で創る巨大ネットワークー合成2次元シート化合物で目指す水浄化
近年の急速な合成有機化学の発展は、比較的小さな有機分子であれば、原子を自在かつ精緻に配置し、分子を思うままに合成することを可能にしました。しかし、ひとたび、目に見えるほど大きな材料に目を向けると、その扱う原子の数が膨大になるため話は一変します。これまで材料中の原子を自在に空間的に配置することは、ほぼ不可能でした。それに対し、原子の位置を精緻に定める2次元·3次元に広がった網状ネットワーク超巨大分子の合成が新たに提案されています。
本講演では講演者の研究成果を中心に、いかにこのような超巨大分子を合成するかについて概説します。さらに得られる網状巨大分子を「分子ざる」として使うことで、水から汚染分子を取り除く、水浄化の試みについても紹介させていただきます。
———
